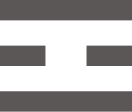房総の山岳集落で隠田を探す

第二十七話
房総の山岳集落で隠田を探す
所要時間:約4時間30分
主要山域:鹿野山(千葉県)
難易度:★★☆(不明瞭な道を含む)
アクシーズクイン・エレメンツでは、山間の集落をつなぐために使われていた生活の道を“クラシックルート”と呼び、古くも、新しい歩き旅を提案する。第二十七話となる今回は、房総半島の山岳集落が点在する田倉地区へ向かい、山岳信仰の対象として尊まれた鹿野山神野寺へと続く山道を辿る。道中では、年貢の徴収から免れるために耕作した田んぼ“隠田(おんでん)”を探しながらの旅路となった。
画像クリックで拡大します
房総半島の南部に位置する富津市。その市街地から、太平洋側に位置する外房の大原へと向かう国道465号線を走らせた車のハンドルを脇道へと向ける。冬の陽光に恵まれるなか、僕たちが辿りついたのは田倉地区の本村という集落であった。
本村集落から鹿野山神野寺まで、江戸の旅人たちによって踏み固められた山道がある。僕たちは、そんな話を聞いてここまでやってきた。その入り口を探していると、道の向こうからひとりの老爺が歩いてきた。登山口の場所を尋ね、集落の昔話についても少し話を聞いてみた。すると、それまで硬い表情で口を閉じていた彼は、表情を和らげて饒舌に話しはじめる。
「あぁ、どこへでも昔は歩いて行ってたよ。学校だって、そうだもん。国道を下っていって、港の方へいったところにある環小学校ってとこまでいってたの。歩いて1時間ぐらいかな。魚を買いにいくんだって、みんな港まで降りていってたよ。いまも行ってるよ、君津まで。あはは。いまは車だけどさ、昔はみんな歩いて行ってたよぉ。でも、このあたりは昔はみんな山道だよ(笑)」
画像クリックで拡大します
森のなかにぽっかりと開けた広場のような山間地にある本村は、十数件の民家が点在する山岳集落である。日当たりに恵まれたところには民家が並び、そのまわりに美しい棚田が広がっている。休耕地となり、ソーラーパネルが設置されているところもあるけれど、ここで暮らす人々の静かな生活を羨ましく思う。そんな田園風景が広がる集落である。
「ここは昔、ぜんぶ畑だったんだ。でも、いつ頃かに田んぼにしたんだね。水はね、鹿野山のほうから流れてきてるの。それを使ってね、谷間を田んぼにして米を作っていたんだ。昔は山のなかにも田んぼをたくさん作っていたんだ。いまから神野寺に行くの? そこから上がっていってね。イノシシなんかも出るから気をつけてください」
御年86歳という老爺は、幼き日を過ごした本村の昔話を披露してくれる。かつての集落には23世帯が生活をしていたけれども、現在は12〜13世帯ほどになってしまったこと。ここまで通じる唯一の道路は、昭和30年代になってようやく舗装路として整備されて車が通ることができるようになったこと。老爺が子供の頃は、毎日1時間歩いて山麓にある小学校まで通っていたことを教えてくれるのであった。
画像クリックで拡大します
本村集落から鹿野山神野寺へと向かう山道は、本村や新田、諸崩、苗割といった集落がある田倉地区に由来して「田倉みち」と呼ばれている。この山道は、室町時代から江戸時代にかけて、山岳信仰の地として房総の人たちが崇めた鹿野山詣でのために使われてきた。
あちらこちらに石祠や地蔵が並ぶ集落のなかには、大きなクスノキの根元に祀られた山神社がある。そこで登山の安全を願うと、老爺に教えられたとおり神野寺へといたる山道があるほうへと向かった。
山道への入り口は、集落の入り口に建つ車庫の横に見つけることができた。そこから後ろを振り返ると、老爺が少し離れたところから僕たちを心配して見守ってくれている。手を振ると、腕を輪っかにして正解であることの合図を送ってくれるのであった。
画像クリックで拡大します
筑波山や榛名山と並び関東三大修験道に数えられる鹿野山神野寺は、598(推古天皇6)年に聖徳太子によって開山されたと伝わる。関東最古の寺といわれ、江戸時代には房総半島一帯から信仰者を集めた。信仰の道は鹿野山道と称され、東西南北に東参道、西参道、南参道、北参道と各方面からの参拝道が整備された。そのなかで、もっとも利用者が多かったのが木更津から小糸の福岡を経由する北参道であったという。
車庫の脇から山道に入っていくと、すぐ左手に大日如来、さらには刳り抜いた岩の壁のなかに立つ石地蔵などを次々と見つけることができる。山道は片側が切れ落ちていたり、両側が切れ落ちていたり、長い年月にわたる人々の往来によって地面が削られた切通しとなったりして神野寺まで続いていた。
房総半島の山岳地形は、とても複雑だ。小さな山や谷がいくつも重なりあい、登山者を悩ませる。尾根筋から切れ落ちたところには広場のようになった場所を見つけることができるけれど、そうしたところに“隠田”が隠されているのでないか? 僕たちは、そんな期待を抱きながら徐々に標高を上げていくのであった。
画像クリックで拡大します
神野寺に到着したのは、田倉みちを辿って1時間ほどしたころである。ここまでは深い森のなかを歩きながら、ときおり房総半島の山々の展望を眺めながら歩を進めてきた。
周囲には、大きな街も、集落もない山中に建てられた寺ではあるけれど、とても立派な山寺である。境内には、大きなイチョウやモミジが黄色や赤色に色づいていた。僕たちは、登山を長く続けられることを願って健脚の祈願をしたり、御茶屋での休憩時間を楽しむことにした。
神野寺から徒歩30分ほどの展望台からは、房総半島の山々が無数に連なる景色を眺めることができる。房総半島の外洋側には、99里(約60キロ)にわたって海岸線が続く九十九里浜があるけれど、この展望台から眺める山々は「九十九谷」と呼ばれる。“九十九の山”ではなく“九十九の谷”と名づけられているのが、なんとも味わい深い。
画像クリックで拡大します
鹿野山神野寺をあとにすると、県道93号線を西の方角へと向かった。途中には、古道標があり、「大山みち、東かの山道、西岩とみへ、北きさらずへ」と刻まれている。そこから舗装路をしばらく歩いていくと、道路脇に「鹿野山鳥居」についての看板を見つけることができる。
ここが、かつて嶺岡往還と呼ばれた鹿野山詣に使われた南参道の入り口となる。国民宿舎跡の囲いを抜けて笹薮のなかへと入っていくと、無造作に「鹿野山」と刻まれた石碑が立っていた。
そこからは、ほとんど踏み跡のない森のなかを、四苦八苦しながら本村集落へと下っていく。道中には、歌川広重が「不二三十六景」で描いた鹿野山鳥居崎という名勝地もある。しかし、江戸時代を代表する浮世絵師の心を打った景色は、いま笹薮に覆われてしまって見ることはできなくなっていた。
画像クリックで拡大します
僕たちは迷いに迷ったあげくに、ようやく山道らしい踏み跡に戻ると、木の葉がまあるく敷き詰められ、型を押したような窪地を見つけた。炭焼き窯跡である。窯跡のうえにある小高い丘には割れた湯飲み茶碗などが散乱しており、かつての生活の痕跡が残されていた。本村集落で出会った老爺は、集落の人たちはみんな炭焼きをしながら生活をしていたと言っていたことを思い出すのである。
そんなときである。
「あれ。隠田じゃないか?」
山道が少し盛り上がった地形の向こう側を覗いてみると、稲科の植物でいっぱいになった広場があった。まもなく本村集落に到着するという頃であった。そのため、もう隠田を見つけることはできないのであろう。そう思った矢先の出来事であるから、僕たちは大いに喜んだ。
さらに隠田から集落に続く道を歩いていくと、さきほどとまったく同じ稲科の植物が一面に広がった別の広場があった。地形を利用した田んぼは、谷間を流れる沢水を堰き止めて作られていた。いまも沢水が流れる音がどこからか聞こえてきている。
作業小屋もあり、こちらは年貢を納めた“正規の田んぼ”なのであろう。隠田を見つけることができて上機嫌のまま本村集落へと到着すると、今朝に訪れたクスノキの下にある神社へと神野寺詣でを安全に終えたことを報告をした。そうして、道に迷いながらも、いや迷ったからこそ思い出深い房総の山旅を終えることができたことに感謝しながら一日を終えるのであった。
文◎村石太郎 Text by Taro Muraishi
撮影◎宇佐美博之 Photographs by Hiroyuki Usami
取材日/2024年11月19日
(次回告知)
次回、第二十八話となる「The Classic Route Hiking」は2025年1月22日(水)更新予定です。北陸地方に位置する福井県は、かつての若狭国と越前国からなり、現在の同県は北側を嶺北、南側を嶺南と呼ばれている。その境界にあたり、峠で隔てられた南北で使用する方言も、文化的背景も異なる境目となってきた「木ノ芽峠」越えの旅へと向かいます。
(アクセス方法ほか)
ACCESS & OUT/出発地点、および終着地点とした本村地区への公共交通機関はないため、JR内房線の上総湊駅からタクシーなどを利用する。鹿野山神野寺を出発地点とした周回コースとした場合は、JR内房線の佐貫町駅を出発する神野寺行きの路線バスが利用できる。
「The Classic Route Hiking」では、独自に各ルートの難易度を表示しています。もっとも難易度が高い★★★ルート(3星)は、所要時間が8時間以上のロングルートとなります。もっとも難易度が低いのは★☆☆ルート(1星)となり、所要時間は3〜4時間、より高低差が少なめの行程です。
Gallery