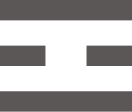浅間神社からの富士登山

第三十一話
浅間神社からの富士登山
所要時間:約16時間(1泊2日)
主要山域:富士山(山梨県・静岡県)
難易度:★★☆
アクシーズクイン・エレメンツでは、山間の集落をつなぐために使われていた生活の道を“クラシックルート”と呼び、古くも、新しい歩き旅を提案する。
第三十一話となる今回は、江戸時代から信仰の対象として崇められてきた富士山へと向かう。江戸時代からの富士登山の玄関口となる「北口本宮富士浅間神社」からの道は、クラシックルートのなかでも“東の横綱”と表現できる存在であろう。山頂までを三区分して、麓部を草山(草原)、五合目までの中腹を木山(森林)、そして五合目から山頂までを焼山(裸地)と呼んだ参拝道を辿って1泊2日の予定で山頂を目指した。
【画像1st-Images】
画像クリックで拡大します
標高約3,776m、日本一の標高を誇る富士山は、古くから信仰の山として崇められてきた。701(大宝元)年、役小角によってはじめての富士登山が行なわれたのち、1577(天正5)年になると富士講の開祖とされる角行東覚(本名・藤原武邦)によって富士の人穴、北口本宮参道の立行石などでの荒行が重ねられ、これにより法力を得て富士信仰を広めることになっている。
このころから、遠く隔ったところから富士山を仰ぎ見て崇める「遥拝」から、次第に修行のために山に登って信仰を深める「登拝」の時代へと移り変わっていく。
富士山信仰が庶民にも広まったのは、江戸時代である。江戸の周辺の村から選ばれた人たちが「講」という集団を作って甲州街道を辿り、片道3日間の距離を歩いて富士山山麓の富士吉田へと向かった。この街には、神職が宿泊場などを提供する御師街があり、富士講にやってきた人々はここで登拝前の一夜を過ごしたのである。富士山信仰は現在も残り、おもに関東の各地域から富士講に訪れる人たちがいるのである。
【画像2nd-Images】
画像クリックで拡大します
「六根清浄、六根清浄、ろっこんしょうじょう」
江戸時代から続く富士登山への玄関口となる北口本宮富士浅間神社から、富士山の方角へ。気持ちがいいほどまっすぐと続く遊歩道を伝って、富士山麓に広がった森のなかを歩いていく。雨後の爽やかな微風がときおり吹いてきては、ほてりはじめた頬を冷やしてくれるのである。
1964(昭和39)年、富士吉田から富士山の五合目までをつなげる富士山有料道路(通称・富士スバルライン)が開通するまで、この道を伝って登山者たちは富士山登頂を目指した。
「六根清浄、六根清浄、どっこいしょ」
富士山に登って身を清めたいと願った人たちは、欲や迷いを断ち切ることを願って「六根清浄」と唱えながら山頂を目指した。彼らは、白装束に金剛杖をつき、足元はわらじや足袋という出で立ちで、人間に備わる六根である眼、耳、鼻、舌、身に加えて、第六感である意(心)を清らかにすることで、己のけがれを取り除こうと唱えたのである。
冗談のようではあるけれど、重い腰を上げるときにはっする「どっこいしょ」の語源は行者たちが唱えた「六根清浄」がなまったものという俗説がある。
【画像3rd-Images】
画像クリックで拡大します
浅間神社の鳥居は、富士山の「富」の字から点を省いた「ワ冠」の「冨士山」が刻まれている。これは、ウ冠の点を人に見立て、富士山の山頂には人を立たせることを禁じた禁足地であること、その尊さがゆえ下から見上げる山であることを表している。
浅間神社から2時間ほど歩を進めると「馬返」となる。ここから先は道が険しくなり、馬を引くことができなかったため、馬方たちを引き返させた場所である。
馬返の横には、「大文司屋」という茶屋がある。江戸時代に開業した茶屋は、スバルラインが開通したことで登山客が激減。廃業に追い込まれてしまったものの、初代の安左衛門から6代目となる現オーナーの羽田徳永さんによって56年ぶりに営業を再開している。
朝8時30分、ちょうど開店時間に通りかかると茶屋前に置かれたベンチに腰掛けた。あんみつを注文すると、羽田さんは調理場で手を動かしながら「最近は、昔ながらの浅間神社からの富士山を歩く人も増えているんですよ。とくに海外からの人が多いですね」と話す。
【画像4th-Images】
画像クリックで拡大します
羽田さんは、父親であり、大文司屋の5代目となる羽田重正が廃業を決め、その後は明治大学山岳部が「明大山荘」として改修が続けられたこと。平成の時代になってからは、富士吉田市が管理する休憩所として利用されていたことを教えてくれた。そのため、五合目以下の茶屋や山小屋のほとんどは残念ながら倒壊してしまったが、大文司屋の建物は無事であったのだ。
馬返から、本格的な登山が始まる。富士山は地表が溶岩で覆われているため、雨が降っても地下にすぐに浸透するため「川のない山」と言われる。ここのところ雨がよく降っていたためであろうか。本来は、水無沢となる沢筋から爽やかな水の流れる音がこだましている。
コメツガやトウヒに覆われた森のなか、一合目、二合目、三合目と徐々に標高を上げていく。途中には、スバルラインが開通した1960年代以降に廃業した茶屋跡の建物が倒壊寸前の状態でいくつも残されている。その様子を見て、営まれていた茶屋の多さに驚かされるとともに、江戸時代から続く富士登山がいかに盛んだったかをうかがい知ることができる。
【画像5th-Images】
画像クリックで拡大します
木々の隙間がまばらになりはじめ、強く太陽光がさしはじめると、まもなく佐藤小屋のある五合目となる。ここからしばらく歩くと、登山客であふれかえる喧噪のなかへと突然に放り込まれる。馬返からの静寂が、嘘のような賑わいである。
五合目までの茶屋や山小屋は木造だが、ここから先の山小屋は石造りの建物となる。富士山にある山小屋は、富士吉田の御師街で働く人たちなどがはじめた宿や休憩所などがはじまりであったと聞く。登拝者で賑わう山腹に、休憩をするための茶屋や山小屋を建てれば一稼ぎできるのではなかろうか。そんな野望をもって建てられた小屋は、森林限界を超える手前の五合目までは周囲の木々を使い、樹木が育たない五合目よりも標高が高いところでは溶岩石を使って建てたのである。
五合目からは背の高い樹木がまったく育たない山道を、ひたすら頂上を目指す。五合目から六合目、七合目へと汗を拭いながら標高を上げていく。頂上が見えているのに、なかなか近づかない。そんな時間が過ぎていく。しかし、今宵の宿とした八合目にある「太子舘」に到着するのはまもなくである。
【画像6th-Images】
画像クリックで拡大します
夜明け前の午前3時30分、僕たちは出発の準備を整えて太子舘をあとにした。ほかの登山者たちのほとんどは、山頂でのご来光を拝むために午前2時頃には出発してしまったようだった。そのため、山小屋のなかは静まりかえっていた。
歩きはじめてから1時間ほどが経過すると、東の方角の雲がオレンジ色に輝きはじめて、太陽が顔を覗かせた。山頂からではないけれど、ここから眺める日の出でも十二分に美しい。真夜中から歩きはじめるのではなく、たっぷりと睡眠をとったあとで八合目、九合目あたりで日の出を拝もうと考えていたのである。
山頂付近の酸素量は、低地の2/3程度の酸素量である。空気が薄く、息が切れて苦しさが増してくる。それでも昨晩はぐっすりと睡眠をとることができたから、心も体も、まったくもって快調である。
【画像7st-Images】
画像クリックで拡大します
午前7時、山頂にある久須志神社の鳥居をくぐると、僕たちは登頂を祝うハイタッチを交わした。鳥居のまわりでは、ようやく山頂に到着したことを喜ぶ笑顔で溢れていた。疲労困憊して、顔をうつむいたまま休憩をしている登山者の姿もある。老若男女を問わず、肌の色もさまざま。
みなの嬉しそうな姿を見ながら、僕たちは富士山の噴火口を一周する「お鉢まわり」へと出かけることとした。現在の富士山は、年間登山者数20万を越えるという。山頂を目指す動機も変わった。当初は信仰目的であったものの、江戸時代後期になると一生に一度は山頂に立ってみたいという「物見遊山」の傾向を強めていった。
僕はこれまで五合目から出発する富士登山に、どこか達成感を得るためだけに登っているような気持ちがあった。しかしながら、山麓から歩きはじめることで不思議と一歩一歩を楽しみながら山を登っている感覚になるのである。
歴史ある道として、現在も麓から舗装路を歩かずに山頂へと向かうことができるのは、北口本宮富士浅間神社を起点とした吉田口登山道のみ。山麓から歩くことで、数百年前の人々と同じような気分に浸る。そんな富士登山を、是非とも今夏に経験していただきたい。
文◎村石太郎 Text by Taro Muraishi
撮影◎松本茜 Photographs by Akane Matsumoto
取材日/2024年9月9日〜10日
(次回告知)
次回の「The Classic Route Hiking」は7月30日(水)更新予定です。第三十一話で向かうのは、東海道や甲州街道といった五街道のひとつ中山道の最大の難所であり、五街道のなかでももっとも標高が約1,531m和田峠を越えます。中山道は別称で姫街道とも呼ばれ、かつては皇女和宮をはじめとした嫁入りの道としても使われた歴史を探ります。
(アクセス方法ほか)
ACCESS & OUT/出発地点とした北口本宮・富士浅間神社までは、富士急行線の富士山駅から徒歩15分ほどで到着する。自家用車の場合は、駐車場のある馬返しを出発地点としても充分に楽しめる。復路は、山頂からそのまま浅間神社夜馬返まで歩いてもいいし、五合目からは富士急バスの路線バスで富士山駅まで向かう。
「The Classic Route Hiking」では、独自に各ルートの難易度を表示しています。もっとも難易度が高い★★★ルート(3星)は、所要時間が8時間以上のロングルートとなります。もっとも難易度が低いのは★☆☆ルート(1星)となり、所要時間は3〜4時間、より高低差が少なめの行程です。
Gallery