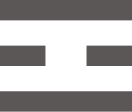お婆たちが洋服を買ったツヅラト峠

第三十三話
お婆たちが洋服を買ったツヅラト峠
所要時間:約4時間
主要山域:ツヅラト峠(三重県)
難易度:★☆☆
アクシーズクイン・エレメンツでは、山間の集落をつなぐために使われていた生活の道を“クラシックルート”と呼び、古くも、新しい歩き旅を提案する。第三十三話となる今回は、熊野古道の伊勢路にある「ツヅラト峠」へと向かう。
2004年、世界遺産に登録された熊野古道とは、熊野三山を詣でるための5つのルートのうち大辺路、中辺路、伊勢道を総じて呼ぶもの。そのなかで、伊勢神宮からのルートとなる伊勢路は、庶民の道として大勢の巡礼者が往来したことで知られる。伊勢路なかで、荷坂峠道が主要な紀州の国への玄関口となってからも、伊勢の国との境界として昭和初期まで生活道として使われていたのがツヅラト峠である。
画像クリックで拡大します
今回、旅の出発地点としたのは、JR紀伊本線の梅ヶ谷駅である。JR四日市駅から電車を乗り継いで約3時間、単線になったレールを走ってきた車両が無人駅のホームに滑り込む。車内にある降車ボタンを押すと「バシャー」という音を立てて扉が開き、冷房がよくきいた車内に湿度をたっぷりと含んだ熱い空気が入り込んできた。
駅から降りていくための階段は、ホームのちょうどまんなかにあった。細い通路になった階段を下っていくと、苔で覆われたコンクリートの壁のあいだから剥き出しになった線路の下をくぐっていく。
通路を抜けると、ぱぁっと周囲が明るくなる。目の前には、八柱神社の境内が広がっていて、青々とした葉っぱを広げた大樹に覆われている。ここは、伊勢と紀伊の国境となるふたつの峠、ツヅラト峠と荷坂峠が合流する熊野古道における交通の要である。境内の奥へと歩いていくと、見事な狛犬に守られた本殿があり、僕たちはそこで今日一日の安全を祈願するのであった。
画像クリックで拡大します
八柱神社からは、舗装された県道を案内板に従っていき、ところどころで林のなかに通された脇道へと誘い込まれれるようにして進んでいく。県道から見える景色は、谷間に作られた田んぼの奥に民家があり、まだ小さな稲穂が微風に吹かれながら踊っていた。
風情が増してくるのは、東屋やトイレがある定坂小公園を過ぎたあたりからである。右へ、左へと蛇行していた大内山川を離れ、その支流となる栃古川沿いの道を辿ることとなる。その川面からは、朝靄が深く立ちこめていて幻想的な風景を作り出している。橋のうえから水かさを増した川の流を眺めていると、雲の隙間から強烈な太陽光が差し込んできた。
栃古川との分岐点の少し手前では、森のなかに置かれた33体の観音像を見ることができる「定坂四国三十三観音」がある。小高な丘のなかに小道が伸びていて、渦を巻くように奥へ、奥へと螺旋状に続いている。その小道を進んでいくと第一観音像から第三十二観音像までが出迎えてくれるのである。32体目を見つけたあとで、最後の33体目を探そうとしていると、螺旋上の道から外れた脇道に置かれているのを見つけるのであった。
画像クリックで拡大します
定坂四国三十三観音から、ほどなくすると舗装路との分岐点となる。そこには「熊野参詣道 ツヅラト峠道」と刻まれた立派な石標が立てられていた。急勾配になった峠道を越えるためであろう。握り手をきれいに削った木の杖がずらりと並べられていて、誰でも使えるようになっている。その横にある箱のなかには、たくさんの熊鈴が入っていた。僕は、そのなかからひとつを取り出して、腰ベルトにつけてみる。
チャリン、チャリン。
チャリン。
チャリン、チャリン。
心地よい熊鈴の音を聞きながら、雨で濡れた峠道を伝って一歩、また一歩と標高を上げていく。足元でガサゴソとなにかが動いたと思ったら、大きなカエルがピョンっと屈伸をしつつ草のなかへと逃げ飛んでいった。岩の隙間からは、真っ赤なサワガニが顔を覗かせて、僕たちの姿にびっくりして右へ、左へと逃げていくのである。
画像クリックで拡大します
湿り気をたっぷりと含んだ森のなかは霧状の靄がかかり、僕たちはそのなかを汗を滴らせながら歩いていった。視界がパァッと開けたかと思うと、ツヅラト峠へと到着したことを知る。東屋が置かれているところから、尾根をさらに進んでいくと紀伊の国となる熊野灘の海岸や山並みを見わたす展望台へと到着した。
展望台の木の根元に腰を降ろして休憩時間を楽しんでいると、海から越えてきた微風が火照った体を冷やしてくれる。手にした木の杖のうえに顎を乗せていると、あまりの心地よさにウトウトとしてきて思わず目を閉じてしまった。
ハッと我に返るかのように目を覚ますと、おもむろに持ってきたオニギリを取り出して口に頬張った。また、ウトウトとしてくると、この峠道を往き来した人たちのことを想像するのであった。
画像クリックで拡大します
このまま微風に吹かれながら昼寝をしていたい。けれども、かつて「うおまち」と呼ばれた紀伊長島へと向かわなくてはならない。「ヨッコイショ」と、重い腰をあげて急坂をくだりはじめることとする。石畳が敷かれた山道は滑りやすく、右へ、左へと曲がりながら里の集落へと続いていく。
標高約357mの峠へといたるツヅラトとは、九十九折のことを表す。それまでの主要路であったツヅラト峠は、江戸時代以降は荷坂峠道に紀州への玄関口をゆずったものの、昭和初期まで近隣住民たちの生活道として使われてきたという。
山道が終わり、僕たちは志子川沿いにある舗装路を歩きながら、いま越えてきた山道を見返すようにうしろを振り返った。そのとき、自転車に乗った男性が「どこから来たの?」と川の反対側から声をかけてくれるのであった。
画像クリックで拡大します
自転車に乗った男性に、ツヅラト峠を越えてきたことを伝える。すると、彼はアイスキャンディを手にしながら「こっちへおいで」と手招きをしてくれるのである。
そんな誘いにのって、民家の軒先へと向かう。彼に昔のツヅラト峠について尋ねると、「熊野古道だなんて知ったのは、世界遺産になってからだね」と話して、顔をゆがめるのであった。
「昔は、ただツヅラト峠っていう名前があっただけ。わたしが子供の頃は、遊びで登る山だったんですよ」
そんな話をしていると、部屋のなかで涼んでいた、お婆も話しに加わった。
「昔は、若い頃はね、しょっちゅう歩いてたよ。梅ヶ谷まで行ってたの。あそこまで行ってね、買い物して帰ってきてたの。魚をこっちから持っていって、向こうで洋服とか、ほかのものに交換して帰ってきていたんですよ。梅ヶ谷の人は、伊勢まで行って洋服とかそういうものを仕入れてきてたんです」
画像クリックで拡大します
お婆は「昔の人は偉いわ」と話すと、「今はみんな簡単に車で行って帰ってくるだけでしょ。今の人は歩かへん」と笑って、淹れたてのコーヒーを差し出してくれる。
「子供の遠足っていったら、ツヅラト峠まで行ってたんですよ。梅ヶ谷の駅まで行って、電車で帰ってきていたんです。ほかに遊び場があらへんから、よくいってたよ。その目の前にある川も、昔はもっと水が多くてね。よく泳いでましたよ。みんな、泳いでたね(笑)」
ふたりと別れてから、今日の終着点とした紀伊長島駅まで30〜40分の舗装路歩きとなる。アスファルトで覆われた道は、午後の日差しによって照り返しが強くて体温をどんどんあげていく。先ほどまで包まれていた優しい微風、心地よい川の音はもうここにはない。お婆たちが思い出を話してくれたような、大人の遠足もまもなく終了である。
文◎村石太郎 Text by Taro Muraishi
撮影◎宇佐美博之 Photographs by Hiroyuki Usami
取材協力◎モデラート(三重県四日市市) https://moderateweb.com
取材日/2025年7月15日
(次回告知)
次回の「The Classic Route Hiking」は10月29日(水)更新予定です。第三十四回では、山中で木を切り出して、漆器のもととなる木材を切り出していた木地師の生まれ故郷である滋賀県近江氏の蛭谷町にある山間の集落へと向かいます。
(アクセス方法ほか)
ACCESS & OUT/出発地点としたのは、JR紀伊本線の梅ヶ谷駅。JR四日市駅から電車を乗り継いで約3時間ほどで到着する無人駅である。ゴール地点としたのは紀伊長島駅で、往路と同じく四日市などへと戻るといいだろう。
「The Classic Route Hiking」では、独自に各ルートの難易度を表示しています。もっとも難易度が高い★★★ルート(3星)は、所要時間が8時間以上のロングルートとなります。もっとも難易度が低いのは★☆☆ルート(1星)となり、所要時間は3〜4時間、より高低差が少なめの行程です。
Gallery