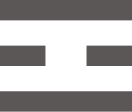伊豆半島に残された生活古道

第二十九話
伊豆半島に残された生活古道
所要時間:約12時間(1泊2日)
主要山域:高通山(静岡県)
難易度:★★☆
アクシーズクイン・エレメンツでは、山間の集落をつなぐために使われていた生活の道を“クラシックルート”と呼び、古くも、新しい歩き旅を提案する。第二十九話となる今回は、伊豆半島の海岸線沿いに残る古い生活道を辿る。
伊豆半島の海岸沿いに点在する集落から、隣の集落へ向かったり、山間の集落から、海沿いの集落へと農産物と海産物の交易のために往き来をするために使われた生活道がある。近年になって舗装路が整備されるまで使われた生活古道は、ほかでは味わうことのできない魅力満載の海岸線歩きの旅路となった。
画像クリックで拡大します
伊豆半島の最南端に位置する石廊崎。荒々しい海岸線に突き出した岬へと向かっていくと、次第に視界が開けてきて、目の前には広大な太平洋が広がっていた。ここからの景色は、遙か8,000km彼方にある米国本土まで見渡せるかのような気分になってしまう。
旅の出発点として、選んだのは石廊崎である。とはいえ、有名な灯台がある岬ではなく、入り江のなかに民家が並ぶ石廊崎港なのである。かつて長津呂と呼ばれた集落がある湾内は、帆船で外洋を渡っていた19世紀の中頃まで、風待ちのための港として利用されていた。
生活古道への入り口は、石廊崎港を出発してから県道16号線へと出て7〜8分ほど辿ったところで見つけた。舗装路の右手へと向かう林道のような山道があり、「南伊豆歩道」と示された案内板に従っていく。すると、その山道が深い森のなかへと誘い込まれていくのであった。
画像クリックで拡大します
古い山道の脇には、あちらこちらに古い石積みが残されており、岩石を削って作った階段は風化して丸みをおびていた。倒れた地蔵が転がって、土に埋もれかけていたり、酒瓶が散乱するなど生活痕がいたるところで見られるのである。少し高台になったところには、四国八十八ヶ所の供養塔が潮風で風化しながら出迎えてくれていた。
山道から、森の奥のほうへと視線を向けると、石積みがいくつも重ねられて平らな土地を作ったような痕跡がある。長津呂にかつて住んでいた人たちが作った、集落跡であろうか? 僕は、そう想像していた。いまは海岸線に集落があるけれど、昔は強固な防波堤を作ることはできなかった。だから、津波などの被害を恐れた人々が高台の安全な場所で生活をしていたのであろう。
しかしながら、そのような記録は残されていないようだ。100年ほど前の地形図で探しても、ここに集落跡は記されていない。これらは、土砂崩れなどで道が塞がれないように、生活道として使った人たちが石積みを作って守っていたというのが真相である。
画像クリックで拡大します
ひとつめの山道から県道へと出て、舗装路を歩いていくと、左手に仲木の集落へと向かう「中木 0.2km」と示された道標を見つけることができる。そのまま小道を下っていくと、海岸線に並んだ民家が見えてくるのであるけれど、ここで僕は背後に不思議な気配を感じた。その気配のもとを確認しようと、後ろを振り返ると、垂直の岩壁の真ん中に、深くて大きくて、ぽっかりとした空洞がある。
昭和初期まで、伊豆半島で採掘される伊豆石が切り出されていたといい、その跡が空洞になって残されているのである。「石丁場」と呼ばれている石切り場は海岸線に数多く残されているけれど、これは船で運ぶことを容易にするためであった。
伊豆石は、江戸城の建造のために切り出されたことで知られている。けれど、このあたりで採掘された石材は江戸に運ばれたわけではなく、近隣の神社や仏閣、学校などの建造のために使われたという。足元から垂直に切れ落ちるように斫られた石丁場は、縦横になった波状の切り跡が残されており、真っくら闇になって奥深くまで続いていた。
画像クリックで拡大します
仲木の港から、高台になった集落の墓地を抜けると山道は急勾配の階段となった。そこで一気に標高を上げていくと、目の前に石棺のような構造物があらわれた。小さな庭のようになった石積みの奥には、岩壁を刳り抜いて作った石室が見えている。
日和田山の山頂に位置する、石室「念仏堂」であるという。ここは、集落の長老たちが航海の安全を願って念仏を唱えた場所で、前庭のような場所には、いつからか木の種が落ちて、いまでは幹回り40〜50cmほどに成長している。
そこからは、ウバメガシのトンネルを上へ、下へと登り下りしながら、次の集落となる入間へと向かった。道中は、強風に煽られながら、茅で覆われた丘の上の稜線歩きである。風速10mを超える西風は、真っ白な波を海面にたたせていた。風に体をあおられ、かぶっていた帽子が飛ばされてしまわないように手で押さえながら進んだ。
画像クリックで拡大します
石廊崎から数えて、みっつ目の集落となるのが入間である。ここまで、目が奪われるような美しい海岸線を望みながら、およそ1時間ごとに漁港に到着した。僕は、その感覚に心地よさを感じていた。通常の山歩きでは、生活の痕跡を感じることはほとんどないけれど、この道は人の営みと営みのあいだを往き来するような歩きの旅をすることができるのである。
さらに入間から吉田の集落へと向かう道中には、壮大な石切り場跡が残る千畳敷がある。採掘された伊豆石は、下田などの町並みで使われた。切り出した名残として、テラス状になった広場には四角く切り出し跡があり、海水がたまってプールになっていた
1日目の宿としたのは、南谷川浜あたりである。吉田と妻良の中間ほどに位置しており、西風を遮ることができる幕営適地である。ここに到着するなり、僕は持ってきた日本酒を取り出して、ひとくち口に含んだ。一日目の無事を祝うハッピーアワーである。太陽が傾きはじめる頃にはタープを張って、その下に寝袋を広げ、夕食の準備に取りかかった。風はまだ強いけれど、快適な夜を心置きなく楽しむのであった。
画像クリックで拡大します
2日目の朝は、日が昇る前からの行動開始となった。ヘッドランプで山道を照らしながら、妻良漁港へと向かった。昨日から天候は一転して、風は穏やかとなり、山道から凪いだ太平洋を眺めるのであった。
妻良の漁港からは、国道沿いを進んで子浦漁港へと向かい、そこからは草原が広がる尾根道を進んだ。ここは昔、茅場として利用されていた場所であるという。茅葺き屋根のほか、墨を運ぶための炭俵などの材料を刈り取っていたのである。
「この集落には、昔は20世帯ぐらい住んでいたけど、いまは7世帯くらい。小学校へは、伊浜まで通っていましたよ。4キロあったけど。国道ができる前、トンネルもなかった頃ですね。中学校は子浦だったんで、そこまでも歩いていってましたよ」
そんな話をしてくれたのは、子浦からさらに進んだ落居集落で出会った老爺である。子浦からの山道を歩き、丸山トンネルを抜けて落居にやってきた僕たちは、そのまま海岸線にある山道を辿っていくつもりでいた。しかしながら、その道は数年前に崩落してしまったと、御年75歳の老爺は言う。いまは通行できないため、民家のあいだを通って国道へと抜ける道を案内してくれるというのだ。
画像クリックで拡大します
老爺に教えてもらったとおりに小道を登って国道へと辿り着き、まもなくすると伊浜の集落である。そこからは、軽自動車が一台やっと通れるくらいの海岸線沿いの舗装路を歩いて波勝崎へと向かうことにした。風が強く、気温が低かった昨日からは一転。体がほてってきて着ていた上着を一枚、もう一枚と脱いでいった。
今回の旅のフィナーレは、高通山である。急な木製階段を登り、汗を拭いながら山頂へと辿り着くと、これまで2日間歩いてきた海岸線が遠く彼方まで続いていた。その反対側を振り返ると、今回の終着地とした雲見の集落も見えていた。
伊豆半島の生活古道は、想像を超えた絶景が続く海岸歩きの旅であった。バスの停留所に立ち寄って発車時刻を確認すると、2日間の汗を流すことができる温泉宿でも探すことにした。そして新鮮な海の幸でもいただきながら、今日もまたハッピーアワーを過ごしたい。
文◎村石太郎 Text by Taro Muraishi
撮影◎宇佐美博之 Photographs by Hiroyuki Usami
取材協力◎サンカクスタンド(静岡県伊豆市)
取材日/2025年2月13日〜14日
(次回告知)
次回、第三十話となる「The Classic Route Hiking」は4月16日(水)更新予定です。房総半島に残された石切り場跡として有名な鋸山へと向かいます。
(アクセス方法ほか)
ACCESS & OUT/出発地点とした石廊崎港へは、下田駅前から運行している東海バスの石廊崎港口で下車する。復路も東海バスを利用して、雲見温泉から松崎などへと向かうといいだろう。
「The Classic Route Hiking」では、独自に各ルートの難易度を表示しています。もっとも難易度が高い★★★ルート(3星)は、所要時間が8時間以上のロングルートとなります。もっとも難易度が低いのは★☆☆ルート(1星)となり、所要時間は3〜4時間、より高低差が少なめの行程です。
Gallery